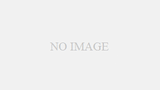はじめに:「生きている」という奇跡を見つめ直す
日々の生活に追われるとき、私たちはどれほど「生きていること」そのものを意識しているでしょうか。
朝起きて、仕事に向かい、食事をして、眠りにつく。
そんな当たり前の日常が、実はどれほど尊いものなのか――それを深く実感する機会は、人生においてそう多くはありません。
私が父の看取りを経験したのは、数年前の冬でした。
病室で父の手を握りながら、その体温が徐々に冷たくなっていく瞬間、私は初めて「命の温度」
というものを肌で感じました。
そして同時に、これまで当たり前だと思っていた日常が、どれほどかけがえのないものだったかを
痛感したのです。
この記事では、父との最期の日々を通して学んだ「生きていること」の意味、そして命と向き合う
時間の尊さについて綴っていきます。
看取り体験は決して悲しみだけではなく、愛と感謝、そして生きることへの深い気づきに満ちた
時間でもありました。
第一章:日常の中で見過ごされる「生きている」という実感
忙しさに埋もれる日々と失われた感覚
現代社会は驚くほど忙しく、私たちは常に何かに追われています。
スマートフォンの通知音、メールの返信、締め切りに間に合わせるための残業。
目まぐるしく変わる情報社会の中で、私たちは「今ここにいる」という感覚を失いがちです。
朝目覚めたとき、「今日も生きている」と感謝する人はどれほどいるでしょうか。
おそらく多くの人は、目覚ましのアラームに起こされ、慌ただしく支度をして一日をスタートさせているはずです。
そこには「生きていることへの実感」はほとんどありません。
私自身も、父が病に倒れるまでは、そんな日常を疑うことなく過ごしていました。
実家を離れて暮らし、仕事に忙殺される毎日。
父との電話は週に1度か2度程度で、それも「元気にしているか」を確認する程度の短い会話でした。
当たり前だった父の存在
母を亡くしてからは、父は1人暮らしをしていました。
週に2回ヘルパーさんに来てもらい、自立した生活を送っていた父。
その姿を見て、私は「まだまだ大丈夫だろう」と安心していました。
電話をすると、いつも元気な声で「大丈夫だよ」と答える父。
その声が聞けることが当たり前になっていて、私はその日常が永遠に続くかのように錯覚していたのです。
人は誰しも、大切なものを失って初めてその価値に気づくと言います。
それは真実です。
私は父の看取りを通して、日常の中にある「生きていること」の尊さを遅すぎるほど遅くになって、知ることになりました。
第二章:父の体調変化と入院―突然訪れた現実

違和感を感じた電話
ある日の夕方、いつものように父から電話がかかってきました。
しかし、その日の父の声は、どこか違っていました。
「調子が悪いので、明日病院に行こうと思っている」
「大丈夫なの?どこか痛むの?」
「いや、なんとなく体が重いんだ。まずは診てもらおうと思う」
電話の向こうの父の声は、いつもより少し弱々しく、どこか疲れているように聞こえました。
私は心の中で小さな不安を感じながらも、「きっと疲れているだけだろう」と自分に言い聞かせました。
しかし、その違和感は的中することになります。
隣人からの連絡と緊急入院
翌日の午後、私の携帯電話が鳴りました。
それは父ではなく、父の隣に住むご近所さんからでした。
「お父さんが入院したよ、必要なものは家から運んだから」
「すみません」
実家はお風呂がないので、お隣さんがお風呂に呼んでくれる仲。
「明日行きます」
「お世話になりました」
翌日病院に到着すると、父はベッドに横たわっていました。
「大丈夫か」
「検査入院だ」
「明日また来るよ」
と別れました。
医師からの告知:「肺腺がん」という診断
数日後、担当医から呼び出されました。
個室に通され、医師は静かに、しかし明確にこう告げました。
「お父様は肺腺がんです。すでにステージが進行しており、治療は困難な状況です。余命は……
おそらく年内、もって12月だと思います」
その言葉は、まるで鉛のように重く、私の心に沈み込みました。
頭では理解しているつもりでも、心がその現実を受け入れることを拒んでいました。
「本人への告知はどうされますか?」
医師の問いに、私は少し考えてから答えました。
「告知はしないでください。父には、穏やかに過ごしてほしいんです」
それが正しい選択だったのかは、今でもわかりません。
ただ、父には最期まで希望を持って生きてほしいと願ったのです。
第三章:病室での日々と「命の温度」を感じた時間
大部屋での父の様子
検査入院が終わり、父は一般病棟の大部屋に移りました。
そこには3人の患者さんがいて、それぞれが病と闘っていました。
「ここの人たちは、がん患者が多いみたいだな」
ある日、父がぽつりとそう言いました。
私は返答に困り、曖昧に頷くだけでした。
父は自分の病気について、どこまで理解していたのでしょうか。
それとも、何も知らないふりをして、私を気遣ってくれていたのでしょうか。
何気ない日常会話の重み
病室を訪れるたび、私は父に好物を持っていきました。
お寿司、鮭とば、父が好きだった季節の果物。
「お寿司買ってきたから食べて」
「おお、ありがとう。美味そうだな」
「鮭とばも買ってきたよ」
「退院したら、また一緒に釣りに行くか」
「うん、そうだな」
何気ない会話。
日常的なやり取り。
しかし今思えば、その一つひとつが宝物のように輝いて見えます。
私たちはどうしても、人との会話を「また次がある」という前提で交わします。
しかし、すべての会話が「最後かもしれない」と思えたら、言葉の重みはまったく違うものに
なるでしょう。
食べることと生きること
父は食べることが好きな人でした。
特にお寿司は大好物で、退院したら回転寿司に行こうとよく話していました。
病状が進むにつれ、父の食欲は徐々に落ちていきました。
それでも、私が持っていったお寿司を1つ、2つと口に運ぶ姿を見るたび、「まだ大丈夫だ」と自分に言い聞かせました。
食べるという行為は、生きることそのものです。
口に食べ物を運び、噛み砕き、飲み込む。
その単純な行為が、どれほど生命力に満ちたものかを、私は父の姿を通して学びました。
第四章:不思議な光の現象と命を感じる瞬間

写真に写り込んだ光の球体
12月を迎える頃、父の体力は目に見えて衰えていきました。
鎮痛剤の量も増え、眠っている時間が長くなりました。
それでも、私が訪れると目を開け、微笑んでくれる父。
ある日、記念に写真を撮ろうと思い、スマートフォンのカメラを向けました。
シャッターを切った瞬間、強烈な閃光が目に飛び込んできました。
「今、何か光らなかった?」
「いや、何もないぞ」
父は不思議そうな顔で答えました。
もう一度シャッターを押すと、再びあの強い光が現れました。
その場では気にせず、後で写真を確認すると――そこには、父の顔の周囲に無数の光の球体が写り込んでいました。
いわゆる「オーブ」と呼ばれる現象です。
オーブ現象とスピリチュアルな解釈
オーブとは何でしょうか。
科学的には、カメラのフラッシュが空気中のほこりや水蒸気に反射して写り込んだものと説明されます。
しかし、スピリチュアルな観点では、魂や霊的な存在が映り込んだものとも言われています。
私は特別スピリチュアルな人間ではありません。
しかし、あの時の写真を見たとき、何か説明のつかない感覚に包まれました。
あの光の粒は、まるで父の周りを守っているように見えました。
あるいは、父を迎えに来た誰かの存在を示しているようにも感じられました。
「今を大切にしなさい」というメッセージ
その写真を見つめながら、私は強く感じました。
これは何かのメッセージではないかと。
「今のうちに、伝えるべき言葉があるのではないか」
「今のうちに、聞いておくべきことがあるのではないか」
「今のうちに、一緒に過ごす時間を大切にしなさい」
あの光は、そう語りかけているように思えました。
真偽はわかりません。
ただ、あの写真を見てから、私は病室に通う頻度を増やし、父との時間をより大切にするようになりました。
第五章:最期の会話と父の旅立ち

「お寿司を一つでいいから」
年が明けて1月に入った頃、父の容態は急速に悪化しました。
痛みが強くなり、モルヒネの量も増えていきました。
意識が朦朧とする時間が増え、会話もままならない日が続きました。
ある日の午後、珍しく父が目を覚まし、私にこう言いました。
「お寿司を買ってきてくれないか。一つでいいから」
その言葉を聞いて、私は心の中で何かが引っかかりました。
まるで何かを予感しているような、父の静かな声。
「わかった。明日、絶対に買ってくるね」
「ああ、頼むよ。じゃあ、明日な」
「また明日ね。おやすみ」
それが父との最後の会話になりました。
静かな旅立ち

翌日の早朝、病院から電話がかかってきました。
「容態が急変しました。すぐに来てください」
急いで病院に駆けつけましたが、父はすでに意識がありませんでした。
ベッドの横に座り、父の手を握りました。
まだ温かい手。
でも、その温度は徐々に、確実に失われていきました。
数時間後、父は静かに息を引き取りました。
看護師さんが優しく布団を整え、私は父の手を握り続けながら、心の中で何度も「ありがとう」と
繰り返しました。
涙は自然に溢れましたが、不思議と悲しみだけではありませんでした。
そこには深い感謝と、父と過ごした時間への愛おしさがありました。
お寿司を買えなかった後悔
父が旅立った後、私はふと思い出しました。
父が最後に頼んだお寿司を、買ってあげられなかったことを。
もし、あの日すぐに買いに行っていたら。
もし、父の最後の願いを叶えてあげられていたら。
そんな後悔が、胸を締め付けました。
しかし同時に、こうも思います。
父はもう、お寿司を必要としていなかったのかもしれない。
あの言葉は、私に「また明日」と約束するための、父なりの優しさだったのかもしれません。
第六章:看取り体験から学んだ「生きていること」の意味
命の温度という実感
父の手を握っていた時間は、私にとって人生で最も「命」を実感した瞬間でした。
温かさがある間は、そこに命がある。
温度が失われていくとき、命もまた去っていく。
「命の温度」――それは単なる体温のことではありません。
人が生きていることの証であり、その人の存在そのものです。
父の手が冷たくなっていく中で、私は強く思いました。
生きている間に、もっとたくさん話をしておけばよかった。
もっと一緒に時間を過ごせばよかった。
もっと感謝の言葉を伝えておけばよかった。
当たり前の日常こそが奇跡
看取り体験を通して、私は「当たり前の日常」がどれほど奇跡的なものかを知りました。
朝起きて、「おはよう」と挨拶を交わすこと。
一緒に食事をすること。
何気ない会話をすること。
そのすべてが、実は当たり前ではないのです。
父がいなくなった今、実家に帰ると強い喪失感に襲われます。
誰もいないリビング。
誰も座っていない父の椅子。
その静けさの中で、私は父の存在がどれほど大きかったかを痛感します。
そして同時に、今ここにいる自分自身の命の尊さも感じるのです。
時間の有限性と今を生きること
人の命には限りがあります。
それは誰もが知っている事実ですが、日常の中でその実感を持って生きている人は少ないでしょう。
私自身も、父の看取りを経験するまでは、時間は無限にあると錯覚していました。
「またいつか」
「そのうち」という言葉で
先延ばしにしてきたことがたくさんあります。
しかし、「またいつか」は来ないかもしれません。
「そのうち」は永遠に訪れないかもしれません。
だからこそ、今この瞬間を大切に生きることが重要なのです。
第七章:写真に残る記憶と生きている証
機種変更前のフォルダーに残る宝物
父の写真は今も、私の古いスマートフォンのフォルダーに大切に保存されています。
機種変更をする際も、あえてそのデータは移さず、古い端末に残したままにしています。
なぜなら、あの端末を開くという行為そのものが、父との時間を思い出すための儀式のようになっているからです。
あのオーブが写り込んだ写真。
父が微笑んでいる写真。
病室で撮った最後の写真。
それらは単なるデジタルデータではなく、父が確かに生きていた証です。
記憶の中で生き続ける存在
人は二度死ぬと言います。
一度目は肉体が死ぬとき。
二度目は人々の記憶から消えるとき。
父の肉体は確かにこの世を去りました。
しかし、私の記憶の中で、父は今も生き続けています。
コーヒーを飲むとき、父との会話を思い出します。
お寿司を食べるとき、父の笑顔が浮かびます。
海を見るとき、一緒に釣りに行った思い出が蘇ります。
記憶という形で、父は私の中に確かに存在している。
そしてその記憶を大切にする限り、父は決して完全に死ぬことはないのだと思います。
写真が語りかける「生きていること」
私が時折、父の写真を見返すとき、そこには単なる過去の記録以上のものがあります。
写真の中の父は、「生きていた証」として、今も私に語りかけてきます。
「一日一日を大切に生きなさい」
「人との出会いを大切にしなさい」
「感謝の気持ちを忘れずに」と。
父が旅立ってから、私は写真を見る習慣が変わりました。
以前は思い出として眺めるだけでしたが、今は写真を通して、父と対話をするようになったのです。
第八章:コーヒーと音楽と共に振り返る命の記録

吾亦紅の歌詞が胸に刺さる理由
すぎもとまさとさんの「吾亦紅」という歌があります。
多くの人の心を打つ歌詞で知られています。
「盆の休みに帰れなかった 仕事に名を借りたご無沙汰」
この歌詞を聞くたび、私の胸は締め付けられます。
『盆の休みに帰れなかった…』という歌詞が、今の私の心に深く響きました。
(引用:すぎもとまさと『吾亦紅』)
吾亦紅の歌詞が胸に刺さる方も多いのではないでしょうか。
全文はこちら → 歌ネットで見る
まさに、私自身の姿を歌っているようで、耳が痛くなるほどです。
父が元気だった頃、私はどれほど実家に帰っていたでしょうか。
仕事を理由に、帰省を先延ばしにしていたことが何度もありました。
今思えば、あの時間はもう取り戻せません。
だからこそ、この歌は私にとって、反省と後悔、そして感謝が入り混じった複雑な思いを呼び起こすのです。
音楽が繋ぐ過去と現在
音楽には不思議な力があります。
特定の曲を聴くと、その時の情景や感情が鮮明に蘇ってきます。
父が入院していた頃、病室で流れていたラジオの音楽。
それらの音楽を聴くたび、私は父との時間を追体験します。
そして、音楽を通して、過去の父と現在の私が繋がっているように感じるのです。
第九章:出会いは別れの始まりという真理
仏教的世界観:一期一会
「出会いは別れの始まり」という言葉があります。
仏教では、すべての出会いは無常であり、いつか必ず別れが訪れると説いています。
この真理は頭では理解できても、心で受け入れることは簡単ではありません。
私たちは、大切な人との別れを想像したくないし、その日が来ることを信じたくないからです。
しかし、父の看取りを通して、私はこの真理の意味を深く理解しました。
出会いがあるからこそ別れがあり、別れがあるからこそ出会いが尊い。
一期一会の精神で人と向き合う
茶道の世界には「一期一会」という言葉があります。
一生に一度の出会いと心得て、その瞬間を大切にするという教えです。
父との最期の会話も、まさに「一期一会」でした。
あの時が最後になるとは思っていませんでしたが、結果としてそうなりました。
もし、すべての出会いを「一期一会」として大切にできたら、私たちの人生はどれほど豊かになるでしょうか。
家族との何気ない会話、友人との他愛ないやり取り、すれ違う人々との短い交流。
そのすべてを「もう二度と会えないかもしれない」という気持ちで接することができたら、言葉も態度も変わってくるはずです。
別れを受け入れることで見える世界
別れは悲しいものです。
しかし、別れを受け入れることで見える世界もあります。
父が旅立った後、私は世界の見え方が変わりました。
街を歩く人々の1人ひとりに物語があり、それぞれが誰かにとってかけがえのない存在なのだと感じるようになりました。
電車で隣に座る高齢者を見ると、その人にも家族がいて、誰かが帰りを待っているのだろうと想像します。
公園で遊ぶ親子を見ると、その幸せな時間がいつまでも続くようにと願います。
別れを経験したからこそ、出会いの尊さがわかる。
喪失を知ったからこそ、存在の価値がわかる。
それが、看取り体験が私に与えてくれた視点の変化です。
第十章:家族との時間を大切にするということ
高齢化社会における親との関係
日本は超高齢化社会を迎えています。
多くの人が、親の介護や看取りを経験する時代になりました。
しかし、核家族化が進み、親と離れて暮らす人が増えています。
私もその一人でした。
仕事の都合で実家を離れ、親との物理的な距離が心の距離にもなっていました。
今の日本社会では、親との時間を作ることが難しくなっています。
仕事、子育て、自分の生活。
優先すべきことは山ほどあり、親との時間は後回しになりがちです。
後悔しないための選択
「親孝行したい時には親はなし」ということわざがあります。
まさにその通りだと、私は身をもって実感しました。
父が元気だった頃、私はもっと実家に帰るべきでした。
もっと電話をするべきでした。
もっと父の話を聞くべきでした。
しかし、その「べき」は、父が旅立った後にしか気づけませんでした。
これは多くの人が経験する普遍的な後悔かもしれません。
だからこそ、この記事を読んでくださっている方には、同じ後悔をしてほしくないのです。
親が元気なうちに、できるだけ時間を作ってほしい。
親の声を聞いてほしい。
親の話に耳を傾けてほしい。
小さな行動が大きな意味を持つ
親孝行は特別なことである必要はありません。
旅行に連れて行くとか、高価なプレゼントを贈るとか、そういうことだけが親孝行ではないのです。
週に一度の電話。
月に一度の帰省。
一緒に食事をする時間。
何気ない会話。
そんな小さなことの積み重ねが、実は最も大切な親孝行なのだと思います。
父との最期の日々を思い返すと、特別なことは何もしていませんでした。
ただ病室を訪れ、父の好きなものを持っていき、他愛ない話をしただけです。
でも、その何気ない時間こそが、今の私にとってかけがえのない宝物になっています。
第十一章:「生きていること」を感じる日常の実践

マインドフルネスと今を生きること
「マインドフルネス」という言葉が近年注目されています。
これは、今この瞬間に意識を向け、あるがままを受け入れる心の持ち方です。
父の看取りを経験してから、私は自然とマインドフルネスを実践するようになりました。
コーヒーを飲むときは、その香りと味に集中する。
歩くときは、足の裏が地面に触れる感覚に意識を向ける。
これらは些細なことですが、「今ここにいること」を実感させてくれます。
そして、生きていることの尊さを思い出させてくれます。
感謝の習慣化
看取り体験以降、私は毎日寝る前に「今日一日に感謝する」時間を持つようになりました。
今日も無事に過ごせたこと。健康であること